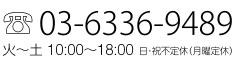闇に向き合う
2016年7月5日の記事です
「あぁ。お父さんです。忙しかとやろ?」
いつも、こんな感じで始まる。父からの電話。
今回ばかりは違っていた。
「あのさ…どうも調子の悪かっさね…」聞けば、4月に交通事故に遭ったらしい。その後は毎日病院へ通っているという。信号停止中、後ろから追突され、左の首~肩、背中にかけての、むち打ち症。
『え??これまで何度も電話で話したろ?交通事故に遭ったとか、お父さん、一言も言わんやったよね?』
(あ~そうか。なるほど。それで。)
前日、愛知にいる妹からLINEが着てた。「姉ちゃーん。今、お母さん、ウチに来とるよー」
私の長崎の実家では、74歳の父母と、39歳になる肢体不自由の弟が3人で暮らしています。母は3年前にアルツハイマー型認知症と診断されました。両親と電話で話すときはいつも二人一緒にいるから、父は電話口で、母のことを話すことが出来ずにいた。
母の症状は確実に進行していて、近頃では短期記憶がほとんど無く、さっき話したことを、又、繰り返して話すといった認知症特有の症状が四六時中続いている。父に対しての攻撃性も強く出るようになって、電話口での父の声からは、相当に参っている様子が感じ取れました。
「今、お母さん、留守にしとるけん電話した。横におったら話したかことのあっても話せんとさね。『何ば話よるとやろうか?』ってオイの話にずっと聞き耳立てとるけん。『私のことば、ボケ扱いしてから!』って、そりゃもう電話切った後が、酷かとやもん。。」
私と会わなかった間、父はずっと電話口で「大丈夫。大丈夫。なーんも 心配せんちゃよか。」
と言っていた。実際は全く、大丈夫では、なかったってことだ。私に心配をかけまいと、全てを自分で背負おうとしていた。
父が、私に対して、弱音を吐いた。
父は大工の棟梁でした。柔道の師範で指導をしていました。声が大きくて、曲がったことが嫌いで、厳格な父。強い父が私に助けを求めてきた初めての出来事です。
———————–
今から5年ほど前に、妹とわたしで父へ提案した事がある。
「ねぇ、お父さん。あっくん(弟)の将来のことやけど、お父さんが元気なうちに、動けるうちにどうしていくか決めようよ。順番からいけば両親は先にいなくなるのはわかっとるし、私たちも、長崎におらんとやし。」
そう切り出した途端に父は、ひどく機嫌が悪くなった。
「毎日、考えん日は、なかぞ。先のこと決めとってその通りになったこと、今まであるか?お前たちに頼らんでもお父さんとお母さんで出来る限りちゃんとやるごとする。お前たちに言われんでも、わかっとる。」
強い口調で、すごい剣幕で、そう言い放ったから、私たち姉妹は、その後二度と、弟の話題に触れることはしなかった。
——————–
「姉ちゃーん。お母さん、今、ウチに来とるよー」
妹から届いたLINEは、父の体調が優れないことを心配した妹が、父の負担を少しでも減らそうとした行動であることは直ぐに理解できた。同時に妹が知らせてきたのは、兄の緊急入院が決まったこと。持病が悪化したらしい。妹は小児喘息で大人になってからも無理のきかない体だから、長崎へ帰省し、掃除が行き届かなくなったホコリまみれの家に泊まることは危険だと父が判断し、家に寄ることを避けるようにしていた。
兄は、実家を離れて就職したが、数年前から腎臓を煩い、なんとか仕事はこなしているようだけれど、ここ数年ずっと投薬中で、免疫力が下がり、入退院を繰り返している状態。私には頼らないと言い放った父だけど、きっともう堪らずに私へ自ら電話をよこしたのだった。
仕事中に会社で受けた父からの電話を切った後、私は軽くパニックに陥っていた。少しの間、思考が停止していて、ようやく事の重大さを受け止め、深刻さを飲み込み、理解し、サロンにいた海老原へひとこと言った。「えびちゃん。実家がピンチ…」そう言葉にした途端に涙が溢れ、次から次へと押し寄せてきて止まらなかった。
スタッフへも、実家の現状は話したことがなかったから、これまでのいきさつと状況を伝えた。すると彼女は直ぐにカレンダーを持ってきて「社長。実家へ帰ってください。ほら、見て。この先、一週間のスケジュール、すべて変更がお願いできる方との予定です。お父さん、雅恵さんの助けを待っていますよ。留守は私が守りますから。安心して行ってきてください。社長。大丈夫ですよ。神様は、越えられない試練は与えないっていうじゃありませんか。大丈夫!」
社長。大丈夫ですよ。
今回も助けてくれたえびちゃんの言葉。これまで何度もこの「大丈夫ですよ」が私のピンチの場面で登場し、助けてくれた海老原の魔法の言葉。信頼のもとに成り立つ安心は、揺らぐ私を繋ぎ留めてくれる。顔が合わせられないスタッフへは連絡網で知らせて、予定をリスケさせて頂いた約束があった先方のすべての皆様が、励ましの言葉をくださった。有り難かったです。
頂いた言葉が、すべて、心の底から有り難かった。
退社し自宅へ戻り、父からかかってきた電話のことを夫へ告げ、「父が心配だから帰省してくるね」と話をする。もちろん彼は、私の実家事情を常に把握してくれているし、いつも冷静かつ的確なアドバイスをくれる最強の協力者だ。今回もまた、同様でした。
「雅恵。どげんしたとか。そげんうろたえるな。全然、緊急事態じゃなかろ?ぜんぶ、想定内やろ?親が老いていくのは初めから決まっとるし、自分たちの状況が常に変わっていくことも、あっくんのことも、わかっとったことやろ?雅恵が全部、決めんでよか。兄弟で、家族で、みんなで話す日ば持てばよか。実家の現状、把握してこんね。親孝行だけしてこんね。
それと、僕が言わんでも分かっとるやろうけど、敢えて言うばい。『ほら!見てみんね!だけんあのとき言うたとに!』だけは、絶対に言うたらいけんよ。気を付けて、行ってらっしゃい。お父さんとあっくんによろしくお伝えください。」
「うん、わかった、ありがとう。」最も信頼する人の『絶対』を受け、6/23~6/30一週間をフリーにし長崎へ帰省した。
以前とはあらゆる状況が変わるであろうイメージは、長崎空港へ降り立った時点で直ぐにリアルになりました。前回の帰省で、到着口まで迎えに来てくれていた両親の笑顔は、もう、そこにはなかった。
「長崎に着いたよ。バスで行くけん」空港から父へ電話を入れ、一人で向かう高速バスの中で、いろんなことを考える。前回、実家へ寄れば良かったな。(今年はじめ帰省しましたが、井手口の祖母のお葬式だったため、実家へは立ち寄らなかったのです…)
バスを乗り継ぎ、1年半ぶりに訪れた家は、私の想像をはるかに越えて、荒れ放題に、荒れていました。
———————-
私の生家は、父が子ども時代を過ごした家で、今は残っていません。
三菱造船所のドックを望む町にありました。
祖父母の新居だった広い大きな家は、祖父が亡くなったあと維持ができず、朽果て、解体された。
弟が歩けない身体と判ったときに、私が思ったこと。
「あぁ。またお母さんを取られた…」
母に甘えたくて母を独り占めしたいのに多忙な母。
私は、母に頼りにされる「しっかり者のお姉ちゃん」と呼ばれる立場も邪魔をして、ほんとうの子ども心は、なかなか打ち明けられなかった。
自分が大人になった今、当時のことを振り返ると、見えてくることがたくさんある。両親は弟の身体のことで、多くを諦め、多くを決断したのだと思います。肢体が不自由ですから「健常者」とは区別され、所謂「身体障碍者」と名付けられ、暮らしの場を別けられました。弟が我が家へ誕生してから、私たち家族は世間から差別される人種へ変化した。
私たち兄弟が通った隣町の幼稚園へ、同じように受け入れて欲しいと園長先生へお願いに行き、幼稚園へ通うのに、どんどん体重が増えていく男の子を毎日、おんぶする生活。バギーを抱えて、バス停から幼稚園までの階段を、車道から自宅までの階段を、どこへ行くのにも坂道と階段ばかり。両親の肉体は、すぐに限界を迎えました。
母は、40歳で車の運転免許を取ることを決めた。
つやつやの長い黒髪は、バッサリ切られ、ショートヘアに変わった。
祖父母が暮らす父の生家を出て、車椅子用に作られたバリアフリーの市営住宅への入居を決めた。
想像だけれど、母の決断は、嫁いで初めて行った祖母への反抗だったのではないかな?と思う。
母は、祖母から壮絶な嫁いびりをされていたことを、私は知っていた。私が夜中にトイレに起きたらいつも、母は、泣いていた。決して愚痴をこぼす人ではなかったから、誰にも気づかれないように、こっそり感情を吐き出していたんだろうと思う。昼間、父は仕事へ出かけて家にはいない。嫁いびりは決まって母ひとりの時ばかりだった。日頃の祖母の言葉遣いで察した当時の幼い私は『お母さんは、私が守る。』という正義感で生きていた気がします。ほんとうの自分の気持ちを隠しながら取り繕ってきた母の脳は、忍耐の限界を迎え、アルツハイマー型認知症という病気に形を変えた。
家があるのに親を置いて、祖父も父も大工なのに、自分で建てた家ではなく市営アパートで暮らすなんて、プライドの高い祖母が許すわけがなかった。きっと相当に揉めたでしょう。想像がつきます。歩けないとわかった弟に祖母は「ウチの家系にはこげん子はおらん。どこの血やろうか」と言い放ったのを覚えている。それでも、両親は弟の成長に合わせて住居を変える選択をした。
その住まいが、現在の実家で、私が帰省して泊まる場所。
————————
実家に着いて扉を開けた途端、鼻をつく異臭。
カビ臭、埃、ショウジョウバエ、そしてゴキブリ。1階に設置される車椅子用の住居は、特にカビと虫の問題が避けられない。冷蔵庫を開けてみると、そこには、形がなくなり元がなんだったのか判らないほど枯れたり溶けてしまっている野菜の残骸らしき茶色い物体。冷凍焼けした魚らしきもの。開封された瓶詰めの調味料はすべて賞味期限2015年で切れていた。
それらは、前回、帰省したときから、もう母が料理をしていないことを物語っていた。届けられた進物、お中元やお歳暮の素麺やらタオルやら海苔やら、たくさんのモノが至るところに溢れかえっている。実家の現状を目の当たりにしたとき、後悔と反省、冷静な目と思考が同時に沸いた。あぁ、やっぱりお葬式の後、実家へ寄れば良かった…悔やんでも悔やみきれない。お母さん、気がつかんでごめんね。懺悔しても、そんなのは後の祭りだ。過去はもう取り戻せないのである。現実を、見ろ!自分!
我に返って、ふと思う。
『いま、日本中にこんな状態の家があと、どれだけあるのだろう?』
胸が苦しくなった。
両親は二人とも、昭和17年生まれ。
父は生まれも育ちも長崎で3才で被爆した。原爆を搭載し長崎上空へ飛んできた飛行機の音は今も鮮明に記憶しているという。逃げ込んだ防空壕でオシッコがしたくなって外へ出たらギラギラと銀色に光る飛行機の機体にただならぬ雰囲気を感じオシッコが止まってしまったと言っていた。
日本に最も『モノ』がない時代に生まれ育ち、モノを大切に大切にしてきた人たち。モノがない時代を支えて、モノを作ってきてくれた人たち。私たち次世代に不自由しない日本を作って来てくれた人たち。
環境が、人を作ります。
捨てられない現実は当然で、捨てられないのも仕方がないのです。そんなの、重々わかってる。
片付けと掃除のための帰省のつもりではいたけれど、頭を過ったのは、「これ、一週間で終わる?」でした。正直なところ、一瞬途方に暮れましたが怯みません。これをやりに来たのだ。逆境に強いのが私。目の前の課題が多ければ多いほど、燃えるのが私なのだ。やるしかない!
大雨警報まで出るほどに雨が続くお天気で、どこまで洗濯が可能かはもうお天道様へおまかせするとして、真っ先に私が取り組んだのは両親の靴への3Dインソール装着。母は、膝の痛みでますます歩けなくなっていた。杖をつきながら、ようやく少し歩けるほどで、痛みをかばうから身体の歪みも出てきていて、認知症も進んでいるから歩けなくなることは死活問題。
父は、仕事の影響もあり若い頃から、ずっと腰痛持ち。さらに、この度の交通事故による首から背中の張りと痛みに苦しんでいた。さらにさらに、二人揃って高血圧。上が130越え、下が80越え。日々の血圧チェックが欠かせない状態。
紛れもない高齢者。現実だ。
普段履いている靴をチェックしながら、ゆるい靴の悪影響を説明し、ゆるい靴はすべて処分。前回東京へ遊びに来てくれた際に私が選んだ靴を日常用に。住まいの周辺での履物には、父は履きなれた雪駄、母は履きなれた下駄。父は若い頃から仕事では地下足袋を愛用していましたし、普段履きにはいつも雪駄でした。母は、着物は普段着ではありませんでしたが、下駄は愛用していたそうです。両親の年代は、終戦後、服が和服から一気に洋服へと移行した時代で、靴よりも下駄の方が馴染みがありますから。
また、体操教室などで運動したりするのにファスナーで着脱できるスニーカーをそれぞれにインソールを作成、足に沿わせるように靴紐を締め、理由を説明しながら「はい。出来たよ。立ってみて」二人とも「わあ!膝が楽になった!」「おお!腰の楽かね!」直ぐにカラダで実感。父の曲がっていた背中はシャンと伸び「むち打ちの痛みが楽に感じる」と言った。身体の仕組みを話しながら、どうして痛みが出るか?どうやって痛みをなくしていくか?歩く必要性を伝え、母をそのまんま散歩に連れて行きました。
弟が歩けないと身体とわかってから40年ほどになる。全くと言って良いくらいに母も歩いていなかった。弟の移動は、ほとんど自家用車へ変わったからです。また、祖母がなくなった後、祖父を介護していた母はさらに忙しく車で移動をしていたから。
「下り坂になると、痛いね…」そう言う母に、下り坂で痛みが出ている部分の負担を減らす歩き方には、本来クッションの役割を担う膝の機能不全について、足ゆびの重要性やふくらはぎをはじめとする身体の背面の筋肉を使う必要があること、筋肉が使われると膝の痛みが消える感覚を身体を動かしながら実際の体験を通して伝える。膝にサポーターを巻き、杖をつき、途中でストレッチをしながら、片道700mの道を二時間かけて何とか歩ききりました。
自宅へ戻ってから直ぐに血圧チェック。
すると「わぁ♪」
久しぶりに耳にした母の明るい声は「ほら!見て!116と62 って出たよ。下がったねぇ。嬉しい!」
そう!そうです。血圧は歩いて自分で下げる。
これが、人の身体です。
「お母さん、膝は?」
「うん、膝はマシになった。少し痛いかな…だけど、足が軽いね。歩くと、気持ちがいいね。いっぱい汗かいて、スッキリするね。」
「お母さん、すごいよね。お母さんの身体、偉いよね。自分で歩いて、血圧下げたとよ。膝の痛みをなくすためには筋肉はたくさん使わんばいけんと。関節の動きをよくするために歩かんばいけんと。身体は動かして使わんば、固まって動かんごとなるとよ。わかるよね?今日から、毎日、歩くけんね。私が長崎におる間に、私が東京に帰ってからも、お母さん一人で歩けるように、一週間で膝の痛み、とるけんね。よか? 歩くよ?」
母は「うん。分かった。歩きます。」と言った。
それから一週間の長崎滞在中は、毎日、母とのお散歩。大雨警報が出ていたのに、お散歩の時間になると、不思議と雨が止みました。2時間かかっていたお散歩は1時間半になり、1時間になり、最終日はたったの40分になった。
長崎を発つ前日の夜、母と、父の、身体を施術で調整する。股関節と骨盤の位置を最終調整。足の踵が真っ直ぐに立つように、足のゆびが真っ直ぐに伸びるように、整えた。
父は言った。
「助けてくれてありがとうな。お父さんの身体ば、こげん楽にしてくれて、まーちゃんは良い仕事しよるなぁ。帰ってきてからずっと血圧の低かもん。お母さんのごとまで、オイは歩いとらんとにね。ほんと、ありがとうね。なんもできんばってん、応援しとるぞ。精一杯、務めなさい。」
母は、片足立ちができるようになった。
姿勢が良くなった自分を鏡に映し、真っ直ぐに伸びた痛まない膝を見て、言った。「雅恵さん。どうもありがとうございます。お世話になりました。本当にありがとうね。」その後、母は私へ、深々と、丁寧にお辞儀をしました。私はそんな母の姿を見て、大切な事を思い出したのです。
「ありがとう」の言葉を教えてくれたのは、両親であることを。
———————–
実家に滞在中、父の配慮のない言葉に傷付き、それが引き金となって攻撃性が出てくる母の様子を度々目にした。お互いを想い合っているはずなのに、愛しているはずなのに、うまく意思疏通が出来ずに苦しんでいる二人の姿を見て、悲しくて堪らなかった。
若かった頃の二人の話。
父が昔、照れながら話してくれました。「お母さんは、キレイかったとよ。髪の長うしてね。吉永小百合んごたった。わぁー!この人と一緒になりたかね~って思うたと。お父さんの一目惚れたい。あ、ごめんごめん。今もキレイかばってんね(笑)」母の花嫁姿の写真を眺めながら、話す父は、少し自慢げにも見えた。それはそれは長い漆黒の髪。透き通るような肌の白さに。静かで穏やかな言葉遣い。優しい笑顔。コロコロ弾むようなきれいな笑い声。物腰の柔らかさ。温かい手。私も母が大好きだ。
母がよく話してくれたのは、父と初めて会った日のこと。
知り合いの家にお邪魔していたら「こんちは~!」と威勢よく入ってきた黒帯で縛った柔道着をひょいと肩に乗せた父の姿が、カッコ良かったとよく言っていました。
「まーちゃんのお父さんは、すごいね。建家(棟上げ)のとき、大工さんは屋根に昇るでしょう。神様の上に立てるのはね、大工さんだけよ。お父さんは偉い仕事、しとるとよ。」
父の仕事を誇りに思っていることを話しながら、毎日、神棚へ榊をお供えしていました。
きっかけはお見合いだけど、互いに好きになって、一緒になった二人は仲が良かったです。
両親が喧嘩している姿は・・・あれ??そういえば、見たことがない。
仲の良かったはずの二人がいがみ合うようになったのには原因がある。
でも、その原因に、当時は家族の誰一人としてまだ気がついていなかった。
私なりに記憶を遡ってみると見えてくるのは、今から17年ほど前くらいに感じた母の微かな変化。
父方の祖母(母を強烈にいじめていた張本人)が亡くなったあと、一人での生活が危うくなった祖父を引き取り母が祖父の介護を始めた頃。これまで仏のように優しくて、他人様の愚痴一つ言ったことのなかった母が、自己主張をするようになった。姑や小姑から受けた嫌がらせのあれこれや、自分がどれだけ耐えてきたかを、堪忍袋の緒が切れたかのように、つらつらと、ブツブツと、愚痴るようになった。そんな母を見て私は「あぁ、お母さんもやっと、自分の気持ちを外に出せるようになったなぁ。良かった」くらいにしか感じていなかったのだけれど、いま思えばそれは、ごくごく軽い認知症の初期症状だったのだ。
仲の良い二人が、好きあって一緒になった二人が、私が愛してやまない両親二人が、認知症のせいで、私の目の前でいがみ合っている姿に、もう黙っては居られなかった。意を決して、口に出す。
父へ、「お父さんはお母さんのこと大好きやったでしょ?今も、大好きやろ?なんでそげん、キツイ言い方すると?お母さんは、『お父さんの大きい声は怖い』って『怒鳴られてるみたいでイヤ』って、いつも、言いよるたい。孫に話すときや近所の子どもたちにはできるとに、どうしてお母さんに対しては、優しい言葉がかけられんと?」
母へ、「お母さんは、お父さんのこと大好きやろ?好きな人のこと、忘れてしまいたくないやろ?お母さん自身が一番不安なのは、想像できる。私がお母さんの立場やったら認知症と診断されて、自分がこれからどうなっていくか怖くて堪らんと思うもん。記憶がなくなっていく不安とか、耐えられんって思うもん。デイケアに行きたくないとか、ボケ扱いされるけん嫌とか、まだ74歳とに80歳以上のご年配の人たちと同様にひどく年寄り扱いされて嫌っていうとも分かる。けど、お父さんの負担ば減らしてあげるのも思いやりじゃなかやろうか?それも優しさじゃないと?」
両親へ思いの丈をぶつけ、泣きじゃくりながら、訴えた。
弟は横で、ずっとニコニコ笑ってる。
「あっくんは、偉いね。何を言われても、動じないもの。功徳を積んだ高い高い魂の人やもんね。お父さんとお母さんの仲介役で、お父さんに怒鳴られてストレスの捌け口にされても何とも思っとらんもんね。あっくんは、自分で手を挙げて『私に不自由な身体をください』って神様にお願いしたとやろ?『五体満足の健康体の有り難さを伝える役目を私が担います』って、生まれてきたとやろ?ねぇ、あっくん。」弟は、黙って、私を見つめる。
そうやって話しているうちにボンヤリしていた母の顔つきが変化する。目に力が籠り、目付きが変わり、目線がしっかり定まってくる。静かに話し始めた母の口調は、さっきまでとは別人だった。
「お父さん。私ね、お父さんがそんなツラいって知らんやったよ。いつでも、何でも、自分で決めてしまうたい。自分で決めてしまわずに、私にも言って。なんでも、話を、して欲しいです。私だって、まだ、話してもらったら分かるとよ。まだ、理解できるとよ。」
しっかり自分の考えを告げた母の言葉は、認知症の母ではなかった。
母は、お料理が得意でしたから台所に立つ母の横にお風呂の椅子を持ってきて、横に並んで様子を見ているのが大好きでした。キレイ好きでお掃除とお洗濯が得意で、私たちが学校から帰宅すると家の中がたびたび模様替えされていた。お布団がふっかふかになっていたり、ハンカチへきれいにアイロンが当ててあったり。次々に料理を作り出す部屋の様子をくるくる変えていく母の手が、まるで魔法みたいで、あの頃の私は母という女性へ恋焦がれ、一番の憧れの存在でした。懐かしく思い出を辿りながら母へ訊ねる。
「ねぇ、お母さん。もう我慢せんでいい。うるさいおばあちゃんも居なくなりました。楽しいことだけ選べは良かよ。楽しくなかったケアには行かんで良いよ。別の楽しいところば探せばいい。行きたくなるところに行けばいい。ストレスないし、穏やかに過ごせるけんね。嫌なことは、何もせんでいいけん。お母さんはさ、何しよるときが一番楽しいと?」
「そうねぇ~楽しいのはね、ご飯作るときが一番楽しい。今日は、何、作ろうかな?何作ったら、みんなが美味しいって言ってくれるかなー?って考える時が楽しい。作ったご飯をみんなが美味しいって食べてくれたときが一番嬉しい。大変だけど、お魚を捌くのは楽しいね!」
「うん。分かった。じゃあできるだけ、お台所に立とうか。お魚買いに行こうね。私、お母さんの鰯の天ぷらが食べたい。作ってくれる?」
「うん。良かよ。明日、黒潮市場にお魚買いに行こうか。お母さんが鰯ば、捌こうかね。お父さん、明日運転して連れていってくれる?」
母は認知症を診断された2013年に車の運転を自ら辞めていた。車の運転がとても上手でした。難しい道や細い道も、狭い車庫入れもスイスイで、運転は楽しいって言ってたけれど、きっと、怖い思いをしたことがあったのだろうな。自分の運転に不安が過ったんだろうと思う。心配性の気質が母にあって良かったなぁと思える。
帰省する度に「何が食べたい?」と食べきれないほどの料理を拵えてくれた母でしたが、このときはもう料理らしい料理ができなくなっていた。亭主関白の極みのような家で、誰よりも早く気がつき、気働きできていた母はもう存在せず、自発的な行動は、ほとんど出来なくなっていた。
父は言う。
「料理はできんごとなったけど魚ば捌くとだけは、できるとよ。だけん、お母さんの造ってくれたお刺身は食べられる。鰯の天ぷらは、まだ自分でできるとよ。お母さんの天ぷら美味しかもんね。鰯の天ぷら食べられてね、俺は幸せばい、まーちゃん。」
ひとつが解決するとまた別の問題が浮上してくる。
母は紹介してもらったデイケア施設が、よほど気に入らなかったのか、ケアには絶対行きたくない、面白くなかったもん、みんなが黙ーーって、何にも喋らず、無言で出されたけどお茶も飲んで良いのか判らず放置されて…と、母は、その日、そのことばかりを一日に何度も何度も繰り返し言っていた。が、どうやら父は、母と一緒に施設見学など行っていなかった様子でした。だから、父には、『相手へ寄り添う』ところの理解不足と、説明不足、伝える時の言葉が足りないことを、改めて伝えました。
母の記憶はどんどん危うくなってきているけれど「愛」が根っこにあって育った「想い」は、記憶がなくなってもなくならないんだって思うから。
そうよ。
母の記憶が完全になくなっても
私の顔が判別できなくなっても
私を娘と認識できなくなっても
愛を伝えることはできるのだ。
互いに肉体が存在する限り。
お互いに生きている限りね。
母娘じゃなく女同士として
新しい関係性を紡げばいい。
時々、ふと、考えることがあります。
母は、記憶がなくなった方が生きるのが楽かもしれないな。と。祖父の介護。姑や小姑から壮絶にいじめらた記憶。戦争のこと、満州での貧しい暮らし。引き揚げ後も貧しくて苦しかった生活のこと。大好きなお父さんが病弱だったこと。自分の婚礼目前でこの世を去ったこと。母から話を聞けば聞くほど苦労話しか出てこないような母の一生。他人へ尽くしに尽くした母は人生の最期に選んだのだと思うのです。
他人から心配され、他人からいつも気にかけられて、他人から注目され、他人から尽くしに尽くされる。
認知症って、そんな病だと思うから。
父は、母に尽くされたから、母は、父に尽くされる。
人生とは、そうやって、プラスマイナスゼロで成り立っている。
本当の記憶はあちらにあるのだから、肉体を持った今の時点での記憶は、別に無くなってもなんの問題はないんだよ。大丈夫だよ、お母さん。お母さんは、私を忘れないし、私もお母さんを忘れない。だからお母さんを見つけて、お母さんを選んで、私は会いに来た。お母さんの娘になったんだよ。だから大丈夫だよ。ね、お母さん。
———————–
母のお腹に居たときの出来事。
一つ上の兄は黄疸が酷く、おっぱいがあげられなくて、ミルクで育ったために断乳。私は、年子で直ぐに母のお腹に宿った。「早すぎる」祖母の一言で私は堕ろされそうになった。だけど母は、私を産んでくれました。どこまでがほんとうの自分の記憶なのかは定かではない。胎児の記憶なのか?大人が話していた言葉を聞いたのか?は明確にはわからない。だけど、私は無意識化でずっと母に捨てられないように生きてきた。捨てられないように良い子でいなきゃと思って生きていた。
私が3才の頃。母の兄の家に子どもが生まれなくて、養子を迎える話が持ち上がっていた。「まーちゃん。ウチにおいで」いつも、そうやって声をかけて私を可愛がってくれる叔母の言葉に、てっきり叔父叔母の子になるものだとばかり思って過ごしていた。母が困っているのなら私が助けてあげようと思っていたからだ。妹の下に生まれた男の子が生後100日で叔父の家へ養子に出された。おっぱいが張って溢れてくるお乳を搾りながら泣いている母の姿を、何度も見た。養子に出され事実上は従弟となった弟は、18歳になった年に生みの親の話を聞かされたそうだけど、やっぱりと思ったそう。弟と私は繋がりが強くて、なぜだかいつも気になる存在で、私が想っているときには、弟も私を想っているらしい。
こうして親に捨てられるかも知れない経験を2回もしてしまって、捨てられないようもっともっと良い子でいなくちゃならないと、たくさん頑張って勉強した。賞をたくさんもらった。母をいじめる祖母から母を守るという正義感と、たくさん褒めてもらえて他人へ自慢できる娘であることで、私の存在する意味を見い出しながら子ども時代を過ごした。
つまり私は、私の人生を、私が主役で生きることを選択してこなかったのだ。
——————————–
アシタスタイルを見つけて、私に会ってくださった方、私の話を聞いてくださった方が、「足から人生が変わる!」と、言ってくださるようになり「足から地球を変える女」は私のキャッチフレーズになりました。キャッチフレーズで終わらせずに、やり遂げるつもりでいますし、それを本気で思っているし、自分の足で歩ける力を持っているすべての人が、自分の足で歩いて疲れを取り除き、身体の不調を手放して、健康になって、幸せになって、笑顔で暮らせる世界になることを願って止みません。冗談なんかじゃなく本当に真面目に、本気で、地球を笑顔でいっぱいにしたいのです。
そう願っているにも関わらず、私にとって最も大切で一番に笑顔でいて欲しい人が、目の前でツラい思いを抱えながら苦悩している。家族が笑顔で過ごしていないのに、地球を笑顔でいっぱいにするなんて嘘っぱちですがな。どう転んでも、出来るわけがない。身近な人を幸せにできない私が赤の他人を幸せに出来るわけがない。私という人間を作り、育み、ありがとうを教えてくれた人たちが、笑顔で過ごしていないのに、私が笑顔でいられるわけがないのです。
向けるべき目は、自分へ。
外ではない。
他人と比べない自分の中の比較。
すべての事象は自分の責任。
因果応報。
私は私が幸せになることを、誰かへ行うより前に、私へする。
先ずは自分を選択する。
どんなに使命を掲げてもどんな正義感も、自分が自分の事を出来ていないのは、実が伴わない虚無の世界でしかない。
—————————–
母の認知症が判明してから、弟は、再びリハビリを始めました。
父はきっと弟へも、母の病状を話したのでしょう。父の手技で毎日やっています。自分の足で立つことを半ば諦めていましたが、改めて補装具を作成し、立つ訓練、歩く訓練を始めました。毎日痛いリハビリを我慢して必死で努力をするようになりました。幼少期にお世話になっていた整形外科の先生との再会により、自立を目指して自分にできることをやると、弟は自分で選択をしました。身体を動かすようになって、足がしっかり着くようになってきてから弟の言葉は、どもることも減り、緊張感もかなり少なくなり、誰が聞いても聞き取れるほどの発声に変わりました。
—————————–
実家にいる間の一週間は、ひたすら掃除。ゴミ袋にしてざっと30袋はあったと思います。そうやって、実家の淀みに、私自身の淀みに、大きな風穴を開けました。それから東京へ戻ってからは、とりあえずしばらくは毎日電話することを決めました。
昨日の朝、母と電話で話したら、私と一週間、毎日散歩をしたいつもの道を40分かからずに杖なしで歩いたそうです。「杖なしで歩いてようかなとおもって頑張ってみたとよ。膝はぜんぜん痛まんやったよ。ありがとうね。本当にありがとうね。」嬉しそうに報告をしてくれました。
父から夜に電話がかかってきたと思ったら「明日、ケアマネージャーさんが来る日になっとるけどさ、絶対会わん!ケアなんていかんけんね!って言い張ってさ、ひどかとばい。困ったなぁ。どげんすうか?どげんしたらよかて思う?」
父は、自然に、私に助けを求めて来ました。
3人とも良い感じです。
——————————-
実家で過ごした私の人生は暗黒時代だった。生きることが苦しくて難しかった。生まれる前から暗闇で、幼少期も思春期も大人になってからも、ずっと真っ暗闇だと思っていました。
しかしそれは紛れもなく私自身が選んだ人生。
ずいぶん長い間、暗闇だと思っていた場所は、私が作った私の影でした。バカがつくほど真っ直ぐで正直な愛の人たちが放つ眩しい光が作り出した陰の暗闇だったのだ。
私が両親を親として選び、両親が作っていく家庭を選び、その中での環境を選び、生きたのです。
その経験のすべては、私そのもの。
私の肉体をこの世に送り出してくれて、今、間違いなく私はここに生きている。
愛していると伝えたい人がいて伝えられる手段がある。
これ以上の幸せが、これ以上の生きる意味が他にあるだろうか?
(人は何のために生きるんだろう?死ぬことが決まっているのになぜ生まれてくるんだろう?)
そんなことを、度々、ぼんやり思っていましたが。
そうか。
私たちは、生きるために生きるんだ。

お父さん。
お母さん。
ありがとう。
私に、光を、ありがとう。