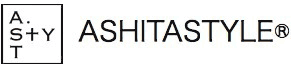着物を着る理由~「靴の着付け」誕生エピソード

井手口が着物を着る理由
アシタスタイル代表の井手口です。
「どうして井手口さんは着物を着ているの?」「足の学校で着物の講座があるのはなぜ?」と尋ねられることもしばしば。理由を書き留めておきます。
実は、アシタスタイルの誕生に際し、「着物」は欠かせなかったアイテムです。むしろ、着物に出会い、自分で着るようになったからこそ、アシタスタイルが完成したと言っても過言ではありません。
アシタスタイルが「日本式フットケア」を謳っている理由でもあります。
きっかけ
井手口がアシタスタイルを創業する、ずっとずっと以前のお話です。友人Tさんのブログの中で、それはそれは可愛くて美しい着物姿を見つけて、とってもトキメキました。Tさん本人へ会った際に直接「素敵なお着物姿で可愛かった!」と告げましたところ、その着物は「アンティーク」と呼ばれる昔の着物であることを教えてもらいました。Tさんご自身は、椎名林檎さんがきっかけで、アンティーク着物の世界を知ったそうです。
「雅恵さん興味ある?着物楽しいよ!似合うと思うし、一緒に着ようよ~」
魅力的な世界へ誘われたものの、次の瞬間、脳裏によぎったのは…(え…でも、着物ってお高いんじゃ…。ていうか、自分ひとりじゃ着られないし…。そもそも、そんな着る機会とかないし…。)
私の顔色が、晴天から曇天へ変わったことをTさんはすぐに察したらしく、「あ。今さ、着れないし~とか、着物って高いし~とか、着ていくところないし~とか、思ったでしょ?」
何でわかったの?!エスパーですか?!
「難しくないし、着物は特別なものじゃないよ。新品や逸品でなければ、着物にも中古品があって、掘り出し物選べば、全身1万円で揃えられるしね!」
「えーー?!いちまんえん?!」
「うん。アンティーク着物も、いわば古着だからさ。もちろん状態にもよるけどね。汚れとか傷み方とか。」
「へぇ~!そうなんだ。でも、着るの大変じゃないの?」
「だって、服じゃん(笑)。慣れてないだけじゃない?昔の日本人は、毎日着物着ていたし、習うとかじゃなくない?洋服だったら子供がボタンを自分で掛けられるようになるとかでしょ」
「確かに。そうだよね。Tちゃんは自分で着るの?」
「うん。自分で着るよ!」
「習いに行ったりとかしたの?着付け教室とか?」
「ううん。見よう見真似で着てるよ。」
「へー!そうなんだ!スゴいね!私も着れるかな?」
「大丈夫だよ。着たい気持ちと、着たい着物があれば着れるから。私もそうだったしね~(^^)雅恵さんも着物デビューしよ!リサイクルの着物屋さんに連れていってあげるよ!今度のお休みに一緒に行こう~」
友人Tさんの頼もしい言葉を受け、早速次のお休みの日に、着物のリサイクルショップ巡りをしたのでした。
宝探しみたいなお買い物
お店に着いたら、とりあえず気になったものを羽織ってみます。
「雅恵さんはちっちゃいから、着られる可愛い着物いっぱいあるね♪」
「ホントだ!!」
アンティーク着物とはビンテージ物。その名の通り古い着物で、明治~大正~昭和初期の着物の呼称です。経年劣化しますから、明治時代の着物などはほぼ残っていませんし、現存するアンティーク着物を年齢で例えると、80~100歳くらいのお婆ちゃんですね。着用できるものはどんどん少なくなっています。
昔の着物は、誰かが自分の寸法で誂えた着物。だから小さいものが多く、寸法もさまざま。(昔の人ってほんとうに身体が小さい人ばかりだったんだなぁ。)改めて思いを巡らせたりしました。
井手口雅恵。
身長155cmなり。
加えて、首が長いために、身丈が必要ない。
さらに、撫で肩のために、裄丈も必要ない。
そんな特徴的なカラダは、既成の洋服の標準サイズが合わなくて、さんざん苦労してきましたから、ちっちゃい自分にピッタリの着物が次々に現れて、選び放題だったことも着物に惹かれていった理由のひとつでもあります。撫で肩で長い首は、もうそれだけで、着物が似合う体型だったのです。
着物仲間たちは、誰もが魅せられ欲しくなる素敵な意匠なのに小さすぎて着られない素敵アンティーク着物のことを「シンデレラサイズ」と呼び、シンデレラサイズの着物を着られる身体サイズの人を「選ばれし者」と呼びました。
私はその後、度々、シンデレラサイズの麗しい別嬪さんたちに出会い、仲間たちから「選ばれし者」と呼ばれるようになり、なんだか、いつも得した気分を味わいました。
(背がちっちゃくて良かった♪)
それまでずっとコンプレックスだった身長と体型が活かせたのです。長年抱えてきた既成の洋服サイズが合わない残念な気持ちとか、解消できなかったモヤモヤがスッキリしたまさに「昇華」と呼ぶに値するであろう感情でした。

アンティーク着物の魅力
美しくて、麗しくて、洗練されていて、大胆かつ、緻密で繊細。贅を尽くし、職人技を惜しみなく表現した、歩くアート作品。それがアンティーク着物。当時なら、私なんぞの庶民が触れることなど絶対に有り得ない素晴らしく見事な逸品の数々が、ワンピースを買うような嘘みたいなお値段で手に入る。
「わーーー!これ、好き!!!」
ハートをブチ抜かれた着物を纏い、鏡を見ると心が踊りまくるのです♪
その感覚、まるで、恋でした。
お手ごろ価格の状態の良い着物とすぐに結べる半幅帯を手に入れて、見よう見真似でとりあえず着てみた私。すると何となく着られてしまった。教えてもらったわけでもないのに。
(あれ?意外とイケるかも?)
(ぜんぜん難しくなかったゾ…?)
「おっしゃー!さぁ!着るぞー!」と気合い入れて始めちゃったからちょっと拍子抜け気味となりましたが、自分一人で着物を着てみたその日は、一日家の中で着物で過ごしてました。
なんだろうか?
懐かしいこの感じ。
守られている安心感。
「私、ただいま」
「お帰りなさい、私。」
そんな会話がなされるような本来の姿というか、自分の居場所というのか、ずいぶん昔から知っている落ち着くその場所に戻ったような不思議な感覚でした。
これって、たぶん、ご先祖様から脈々と受け継がれた「KIMONO遺伝子」なんだろうな。って思いました。
その後は、もう、沼!!!24時間ずっと着物のことばかりを考える日々です。
KIMONO姫が愛読書となる。アンティーク着物好きあるあるです♪
2000年に上京してから始めたカラダと足の探求が実を結び、結果を出し始め求められることが増えてきて2014年にアシタスタイル創業。仕事が忙しくなってアンティーク着物を愛でる機会は次第に減っていたけれど、心と身体は、常に着物を欲していましたから、イベントなど事あるごとに「ここぞ!」とばかりにお気に入りの一枚を引っ張り出しては、めかしこんでお出掛けしました。

自分へのお手当て
高まる胸のドキドキを感じながらたとう紙を開ける。着物を広げ、袖を通し、裾を合わせ、腰紐を「キュッ」っと結ぶ。襟を合わせ、丁寧に丁寧に自分の手を身体へ当てていく所作がとても、好きです。
私が私へずっと「よしよし」ってお手当てしてる感じ。自分の手が自分を癒していくセルフケア。着付けをしている人の一連の所作を見るのも好き。着物を畳んでいる姿を眺めているのも好き。優雅な舞のような美しい動きに、つい見惚れてしまうこともしばしば。着物を着ていると、嫋やか(たおやか)という表現がぴったりだなあと思います。
風の流れや波の動きみたいな自然由来のしなやかな動きが、着物には自ずと表現される感じですよね。
靴の着付け
アシタスタイル・メソッドを伝えようとするとき、どうやっても説明が長くなってしまいます。
・足を本来あるべき形へ導き適正へと整える方法。
・足部アライメントを整え上行性運動連鎖で全身を整える方法。
・足部アーチを回復させる足に特化した教育カリキュラム。
その方法は、歯列矯正にも似ているし、使用する道具は、眼鏡や補聴器にも似ています。弱点を補う道具が医療器具であるのと同様に、アシタスタイルの靴やインソールも医療器具なんだけれども、無資格者の私がそのような扱いで販売は出来ないし、もっと身近で、的確に、たった一言で言い表せる分かりやすい言葉がないかなぁ?毎日毎日考えていました。
アシタスタイル創業5年目にして、ふいに降りてきた表現が 「靴の着付け」 でした。
地球上に暮らす我々は全員、重力の影響を受けながら生きています。ヒトの二足歩行はかなり特殊な動作です。
横にして使っていた身体を縦にし尻尾を失くし、本来足として使っていた部位を手として用い、体毛を失くすことで汗をかいて体温調整しながら持久力を身につけた人類は、重力で押し潰されそうになる身体を広がらないように、壊れないように使うには、強い体幹が必要で、かつ、体毛の代わりになる衣服を欠かすことはできません。
着物を着ると、自然に体幹が使えるようになります。それが着物の仕事でありそうなるように作られたものだからです。
ときどき「着物を着ると疲れるんだけど、なぜだろう?」と仰る方がいますが、私は次のようにお応えしています。
「疲れる理由は貴女の体幹が弱っているせいか、もしくは、着付けの要所が外れた着方をしていて着物に仕事をさせていないかの、いずれかですよ。」と。
小さくて力持ち
先日、84歳のご婦人が、セミナーを受講された記事を書きました。井手口よりも身長が低く小柄なおばあちゃまです。「とっても良い足をされていますね」とお伝えしたら「あら、まあ、恥ずかしいわ~。でも、足なんて褒められることがないからそんな風に言って頂けて嬉しいです。農家へ嫁いだから、毎日、畑仕事していました。お米も作っていたのよ。米俵も、担いでいましたよ(^^)」
米俵一俵がどれくらいの重さかと言えば、なんと!なんと!60kg!
こんな小柄な女性がそんな力仕事を?嘘でしょう?と思うかも知れませんが事実なんですよ。
さらにさらに!他のお客様が教えてくださった別のおばあちゃまのお話だと、その方は山形出身で、なんとおひとりで二俵を担いでいたらしいです。
今みたいに便利な時代ではなかったし、歩くしか移動手段がなかったし、大人たちは皆、朝から晩まで働いて忙しかったから、子どもたちは、歳上の兄弟が歳下の子の世話をしていましたよね。4歳の子が赤ちゃんをおんぶしてとか小学校へ幼い妹をおんぶして通うお兄ちゃんとか普通の光景でしたよね。ご年配の方との交流があるとこんなお話が次々に出てくるから面白い!
そう。日本人って、とっても力持ちでした。
日本文化の中で着物と共に培ってきた足は、足自身が仕事をしていました。足が力持ちで強かったんです。裸足で暮らしていましたしね。動物的歩行姿勢で足のゆびを使っていたんです。暮らしそのものが運動でした。
着物は一枚に繋がった大きな布でしっかり身体を包み、肝心な要所を紐で結び纏めて広がらないようにして束にして使わせる。身体は自ずと「真ん中」で仕事しようとするから、これが自然な体幹トレーニングに変わるのです。
アシタスタイルの「靴の着付け」は、足と身体の研究を続けている時に、Tさんとのご縁から着物と出会い、さらに着物を自分で着たことにより、日本人の身体と道具の関係性、又、それらの研鑽を積んだことで誕生しました。
着物を着ると体調が整います。
着物は、日本人の皮膚であり筋肉で、それこそが着物の仕事だからです。
日本の着物は、着物が仕事をしてくれる、人間工学的スーパーリカバリーウェアです。
ほんとうなら日本人は、着物を着て、畳の上で暮らし、下駄を履けばいいのです。そうすることで、暮らしの中で身体が整う仕組みこそが「習慣」で、先人が大切に大切に気付いてきた「文化」だったのですから。
ですが、もうそんな暮らしは取り戻せないほど日本の生活様式は西洋化してしまっています。
日本人とは名ばかりの西洋人化した日本人へ、着物を着る生活や畳の暮らしはを強いるのは、到底無理な話ですし、着物を着ると気持ちが良い「安心・安全・快適」な、この感覚を、どうやって多くの人に伝えて行こうか?と考えた時、足という名前をした小さなカラダに対して、靴という名の洋服を着せ付ける方法で、着付ける気持ち良さを伝えられるのではないかと考えました。
靴の着付けは、ほんとうの自分の姿へと原点回帰したがるカラダ感覚と、和の心の凪を、現代日本人へ体現するひとつの手段として考案したものです。
今やほとんどの日本人が洋装で身を包み、靴を履いていますから、アシタスタイルの「靴の着付け」を機に、日本人が培ってきた着物や和文化を見直すきっかけとなれば幸いです。
以上、靴の着付け 誕生エピソードです。
「靴の着付け」は、ASHITA・STYLE株式会社の登録商標です。